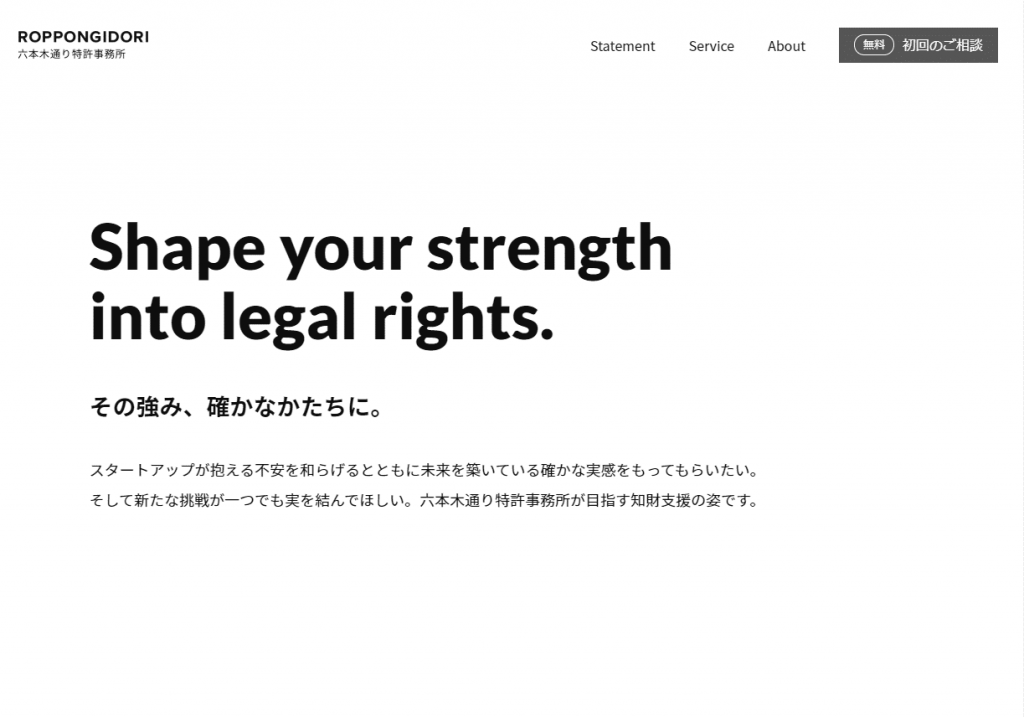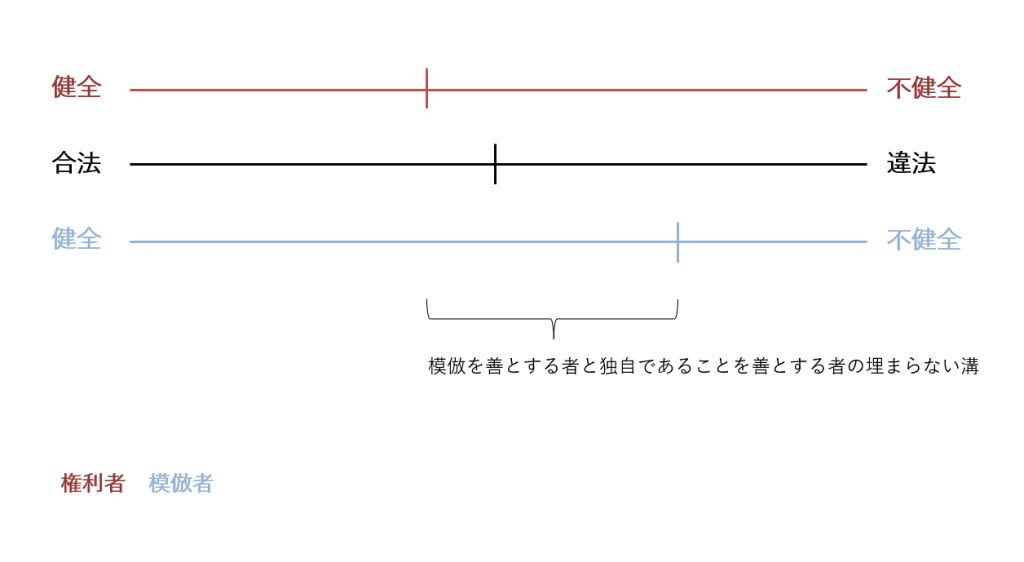発明は、課題とその解決手段の組み合わせです。課題は、抽象度を上げていけば、どのような課題でも既に知られたものに帰着します。逆に抽象度を下げていけば、未解決の課題になっていきます。課題が未解決で独自のものであれば、自ずとそれに対する解決手段も独自のものになります。課題が既に知られているのであれば、なんらかの解決手段も世に存在するでしょうから、より優れた解決手段を見出すことが出来れば独自のものとなります。
課題と解決手段の独自の組み合わせがクリアになり、発明が実り、そして特許出願に至るまでのプロセスについて書きます。
課題設定という第一歩
課題は、既知のものであれ未知のものであれ、スタートアップが事業として取り組むのであれば、解決に値する課題であることが求められます。言い換えれば、スタートアップとして求められる急成長を見込める市場規模のある課題であることが求められます。課題を抽象度を上げて捉えれば対象市場は広がります。しかし、課題を抽象度を上げて捉えれば既存の解決手段が多く存在し、新たに生まれる発明は小さな改良発明になりがちです。十分な市場規模がありつつ、ありふれたものではなく独自性のある課題設定をすることが出来るか否かが発明の第一歩です。
既知の課題を抜本的に新たな視点で解決する発明も当然ありますが、そのような発明は稀有な存在です。たとえばブロックチェーンは、信頼の記録を特定の機関に依存するのではなく数学的に解決するという抜本的に新たな視点をもたらしました。経済的価値の移転が滑らかに行われるためには信頼できる記録が必要であるという基礎的な課題に独自の解を与えようとするとブロックチェーンに相当する発明をすることが求められてしまいますが、解決されるべきにもかかわらず多くの人が気付くことのできていない個別の課題を一早く見出すことができれば、既存の解決手段が存在しないブルーオーシャンになります。
コアコンセプトから発明の完成へ
課題設定の次は、解決手段の方向性が見えてきます。どのような切り口で課題を解決していくのかというコアコンセプトが見えてきます。こうすればいけるだろうという直感的な気付きもあるでしょうし、コードを書いていく中でクリアになることもユーザーインターフェース(UI)をスケッチする中でクリアになることもあるでしょう。アルゴリズムに軸足があるような発明の場合には、この段階で発明が特許出願をする上で十分な水準に達することがあります。ただし、多くの場合はまだ抽象度が高く、発明としてしっかりと実ってくるまで待つことが少なくありません。
特許出願は、権利化したい発明の内容を記述する「特許請求の範囲」という書面と、特許請求の範囲に記述する発明の意義を明らかにするとともにその発明をどのようにすれば実施することができるのかを明らかにする「明細書」という書面から構成されています。明細書において、具体例を通じて発明の意義と実施可能性を説明することができる段階に達して、発明は「完成」したと言うことができます。
コアコンセプトが見えてきた段階は、特許請求の範囲に書くべき内容が見えてきた段階で、スタートアップの立場からすると権利化したい内容が書けるのだから特許出願をするのに十分な水準に達していると感じられるかもしれないのですが、特許法はこの段階ではまだ発明が曖昧で抽象的であると考えます。このような段階で出願をすると単なる願望にすぎないと一蹴されるおそれがあります。単なる願望ではなく実際に社会を前に進めることのできる発明であることを特許庁に伝えることが必要になります。
特許出願に向けて
特許出願の1つの進め方は、新プロダクト又は新機能ローンチの少し前に着手して、ローンチ前日までに出願を完了するというかたちです。このかたちで進めると実際に開発を進める中でコアコンセプトが具体例に落とし込まれていて、発明として完成又は完成間近の段階に来ていますので、出願すべき発明があるか否かの判断がしやすいです。会社として、ローンチ前に出願要否の検討プロセスを入れるというかたちで仕組み化がしやすくもあります。
もう1つの進め方は、開発に先行して出願をしていくかたちです。特許権は、出願日に世界で新しいことが付与の一要件となっていますので、早く出すことができるのであればそのようにすべきです。しかし、発明者が鋭く未来を見抜いているようなケースでは開発に着手する前であっても発明が十分に完成していることがありますが、実際に手を動かして初めてさまざまな気付きが得られ、発明として完成していくのが通常であるため、抽象的な議論に留まってしまうことがあります。特に直近のプロダクトではなく次のプロダクトについての発明を開発に先行して議論するような場合には、手戻りを気にして具体例まで落とし込めずに発明が未完成の状況から進まないことがあります。
ご相談を受けて、特許への取り組みに意欲をもっていただいているにも関わらず、発明が完成しないケースをいくつも見てきました。私としては、ここは発明者が一歩前に踏み出してくれるのを待つほかなく、心苦しくおもうことがあります。起業家が発明するのを見守るだけでなく、起業家がもつ発明する力を引き出す役割を果たすことは出来ないか、最近はそのようなことを考えています。
実施可能性の点についてはこれまで説明をしてこなかったので、具体例の必要性に光を当てて出願が完了するまでのプロセスについて書きました。スタートアップが特許出願に取り組む時期を検討する際の指針にしていただければとおもいます。
2021年2月13日 初回ミーティング時に発明がまだ完成していないことも多く、現在は、そうした状況から特許出願に適した発明を認識するまでのプロセスを数か月かけて行うプランを提供しています。